目次
リモートワークが当たり前になりつつある昨今、プロジェクトマネジメント(PM)の手法も大きく変化しています。
私は約10年にわたってリモート環境で数多くの案件を経験してきましたが、今回はそのなかでも印象的だった大型案件の「リアルな裏側」をお話しします。
守秘義務の範囲内ですが、チーム構成やタスク管理、リモート環境でのコミュニケーションの方法など、少しでもみなさんの参考になる情報を共有できれば幸いです。
大型案件の概要
今回の案件は、デザイナー・開発者・マーケター・翻訳者など専門家が約10名集結したチーム。クライアントはBtoB向けサービスを展開するグローバル企業で、当初のスコープはクリエイティブの刷新、ウェブサイトおよび関連システムのリニューアル、新機能の開発でした。
途中で追加要望が入ってきたり、MA(マーケティングオートメーション)の導入も視野に入ったことで、最終的には開発期間半年+追加開発2ヶ月+MA導入4ヶ月のプロジェクトに拡大しました。
プロジェクトはフルリモート体制でしたが、時差があるメンバーも含まれており、コミュニケーションの難易度は高め。
プロジェクトが大規模化すると、タスクや情報が錯綜しやすく、合意形成が遅れることもあります。そのため、私がPMとして重視したのは「正確な情報共有」と「迅速な意思決定のフローづくり」です。
物理的に集まれないからこそ、オンライン上でいかにチームが連携しやすい仕組みを作れるかが鍵となりました。
PM視点で徹底した3つのポイント
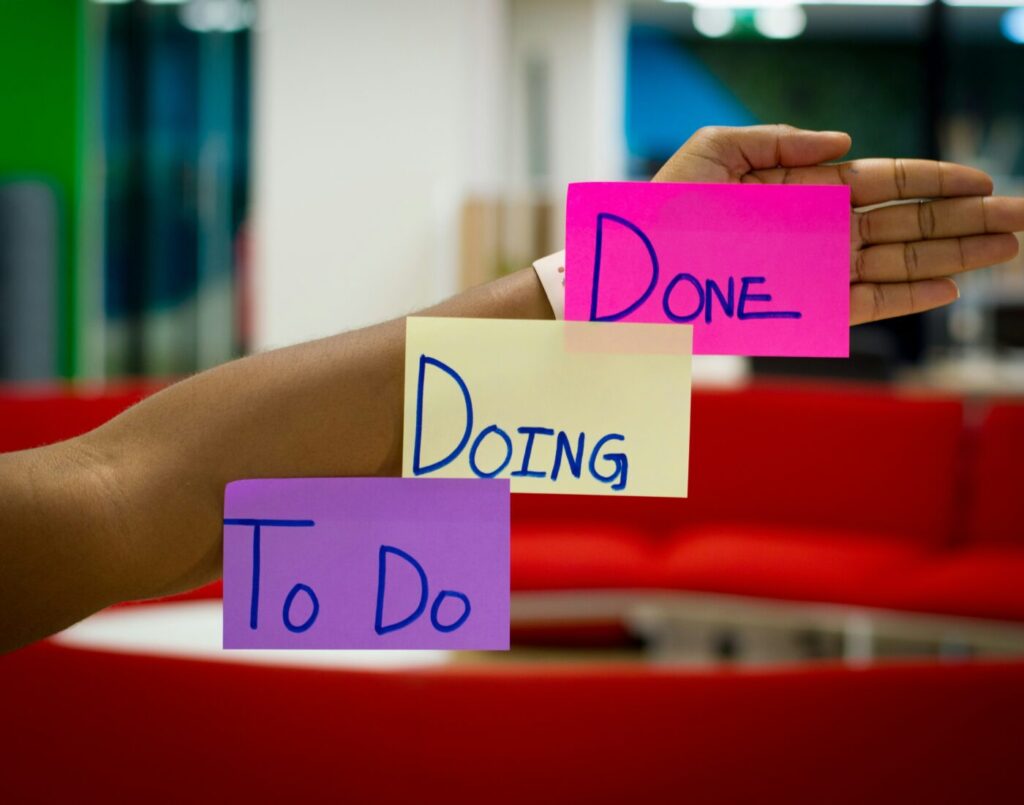
1. ツールをフル活用してタスク管理・ドキュメント管理を一本化
リモート環境では、一度情報を取りこぼすと修正に時間がかかります。そのため、タスクと進捗管理にはAsana、ドキュメント管理にはNotionを導入し、「誰が」「いつまでに」「何をするのか」を可視化しました。
チャットやメールでやり取りを完結させると、後から内容を振り返るのに手間がかかりがちですが、タスク管理ツールに落とし込んでおけば、プロジェクトメンバー全員が同じプラットフォームで状況を共有できます。
また、コミュニケーションの履歴もできるだけツール上に残したり、DMではなく共通のチャンネルを利用することを徹底。小さな変更や微調整も、その経緯が分かるようにしておくことで「どうしてそうなったのか?」という疑問が出たときにさかのぼれるようにしました。
2. 定例ミーティングと進捗報告の頻度を厳守
リモートでは顔を合わせる機会が限られるため、コミュニケーションが不足しがちです。そこで、週2回のチーム内部ミーティングと週1回のクライアント向け定例ミーティングを設定しました。
開発が佳境に入って余裕がなくなる時期は、週1回のまとまったミーティングと毎朝15分のデイリースタンドアップに変更。短いスパンで進捗報告をすることで、小さな問題をすぐに把握し、必要に応じて軌道修正できるよう心がけました。
リモート環境では「問題が大きくなってから気づく」ケースが多々あります。特に、メンバー同士の物理的距離があると気軽に声をかけづらく、問題が潜在化しやすいことも。
しかし、頻度を高めた短いミーティングやレポートの仕組みがあれば、チーム全体が「今何に取り組んでいるのか」「どこに課題があるのか」を常に共有できます。
3. 緊急時の判断プロセスを明確化
大規模案件では、仕様変更や追加予算の可否など、重要な判断を迫られるシーンが必ず出てきます。こうしたシーンで判断が遅れたり迷走したりすると、プロジェクト全体に大きな影響が及びかねません。
そこで、私は「誰が・どのタイミングで・どんなプロセスで判断するか」を事前にドキュメント化し、クライアントとも合意を取っておきました。
たとえば、仕様変更が発生した場合、インパクトを試算して、対応工数とスケジュールを見極める。予算に関わる事項は◯◯さんにエスカレーションする、など具体的なフローを決めておくことで、緊急時でも迷うことなく対処できるように善処しました。
リモートならではの工夫

1. 時差のあるメンバーとどう連携したか
チームメンバーには海外在住者も含まれていたため、そもそもの連絡が「即レスではない」ことが普通でした。
そこで、連絡を受けてから返答するまでのリードタイムをあらかじめ設定。
たとえば「24時間以内には必ず返信する」という最低ラインを全員で共有することで、返事を待つ間に無駄なストレスを抱えなくて済むようにしました。
また、重要なミーティングは時間帯を固定し、内容は必ず録画や議事録で残すようにしました。海外メンバーがどうしても参加できない場合は、あとから録画やAI議事録を見て内容を把握できる体制を用意することで、抜け漏れなくプロジェクトを進行できるようにしました。
2. AI活用で業務自動化
特に繰り返し作業が多い領域や、議事録作成といったルーチンワークにはAIを積極的に取り入れ、効率化を図りました。
最初からAIを使えていたわけではないので、段階的な導入ではあったのですが、たとえばミーティングの議事録はAIを活用して、必要な部分だけすぐに共有・編集できるようにしたり、翻訳が必要なドキュメントをAI翻訳でサポートしたり。
リモート環境では対面よりもドキュメントやチャット上のやり取りが増える分、少しでも自動化できるところは早めに取り掛かると負担が大きく軽減することを実感しました。
プロジェクトの成果と学び

成果としては、当初の開発要件についてはなんとか計画通りにリリースを完了できました。追加要望が発生した場合はスコープを別フェーズに切り出す方針を徹底し、結果的にリニューアル直後のKPI達成率が目標の約120%にまで達したんです。
特にMA導入のフェーズで、新規顧客の獲得プロセスが効率化され、数値面のインパクトが早期に表れたこともクライアントからよい評価を得られた要因の一つです。
私個人としては、「リモートワークだからコントロールが難しい」というよりは、情報共有の仕組みや意思決定フローの未整備こそが最大のリスクになるのだな、と再実感。
物理的距離があろうとなかろうと、大事なのは「誰が何をいつまでにやるのか」を常にクリアにし、問題が起きたときにすぐ対処できる仕組みをつくること。
逆に言えば、ツールやフロー、意思決定プロセスをしっかり設計しておけば、リモートでも十分に大型案件をコントロールできることが実証されたと思っています。
まとめ
リモートワーク時代のプロジェクトマネジメントは、単に「チャットでやり取りすればOK」というわけではなく、ツール選定・ドキュメント整理・定例ミーティングや判断フローの設計など、多方面の準備が必要です。
「リモートだと不安」「大型案件をオンラインで遂行するイメージがわかない」という方も多いかもしれません。ですが、遠隔地のメンバーと連携してきた私の経験から言うと、大切なのは物理的な距離よりも、情報共有と意思決定の「見える化」です。
そこにAIなどの新しいテクノロジーも加われば、距離の壁はますます低くなるはずです。
今回の実録事例が、リモート案件に挑戦されるみなさんのヒントになれば幸いです。


